ビリギャルの坪田先生の「人に迷惑をかけるなと言ってはいけない」をご紹介します!
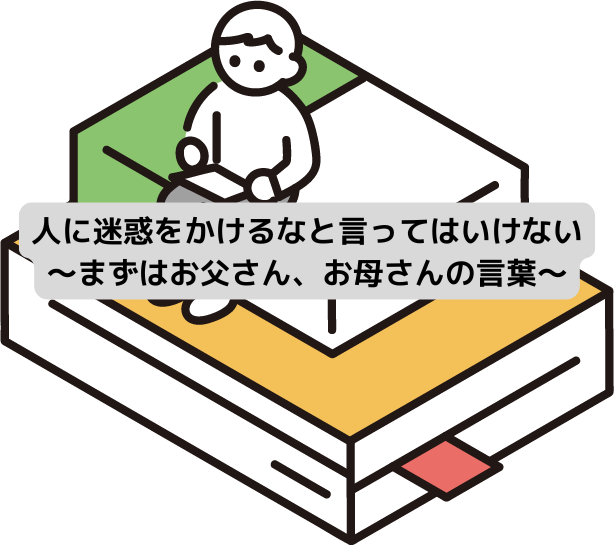

5分ほどで読める記事になっています!
著者について
有名の「ビリギャル」の著者である坪田先生。
これまで1300人以上の子ども心理学を駆使した「子別指導」を実施。
ビリギャルの主人公の様に数多くの子どもたちの偏差値を上げてきている。
人に迷惑をかけるなと言ってはいけない
本のタイトルにもなっている「人に迷惑かけるなと言ってはいけない」という言葉つい子どもへ言ってしまいがちではないでしょうか?
しかし誰にも迷惑をかけずに誰の手を借りずに生きていける人はいません。
「人に迷惑をかけるな」と思い込むことにより「人に助けを求められなくなってしまう」という恐れがあります。
「助けを求めると迷惑をかけてしまう、、」と思ってしまうことから自分でなんとかしようとする、、
そういった何気ないお父さん、お母さんの言葉が子どもにとっては非常に重要であり、どのような声掛けをすることでその子にあった可能性を見せていってあげられるか?
ということが深く学ぶことできる1冊です!



こんな人におすすめです
- 子育て中の人
- 子どもについつい「やめなさい」と制限をかけてしまう人
- 子どもに自分で選択をしていく人生で歩んで欲しいと願う人
人に迷惑をかけるなと言ってはいけない まとめ
「苦手だね」と言われると本当に苦手になる



あなたは算数が苦手だね
子どものころに点数の低いテストを持ち帰った時に「算数が苦手だね」など自分に親に言われたことはないでしょうか?
この様に親から「〇〇は苦手だね」と言われると「自分は〇〇が苦手なんだ」と子どもは自分で思う様になってしまうのです。
ですので「苦手だね」というのではなくできた部分をフォーカスしてあげて「ここができるようになったね」という声掛けを意識すると自分が認めてもらえた様に感じることができます。
水たまりは避けさせない



水たまりがあるから避けなさい
これもよくない声かけです。
水たまりに入って濡れてしまって気持ち悪くなるんだな、イヤだなということを覚えれば次第に勝手に避ける様になるものです。
失敗こそ学びのチャンスであり親が先回りして失敗を回避させてはいけません。
同じく「あの子と遊ぶのはやめなさい」という親では言ってしまいがちな声かけもよくありません。
そのように付き合う人を親が選ぶ様なことしていると結婚相手も、就職先も自分で決められない人間になってしまいます。



子どもにはたくさん失敗させよう
〜したいと言われたらまず質問で返す



お菓子食べたい
という子どもに対して「はいはいお菓子ね」や「お菓子はダメ」ではなく
「お腹すいたの?」などのその子に言いたいことを探る質問をしてあげることが大切です。
おそらく私も含め多くの人は日々の忙しさに忙殺されてどうしても子どもからのこういう要求に対しては何も考えずにお菓子をあげたり、「お菓子はダメ!」などと言ってしまいがちです。
本当の欲求は本人でも気づいていないことが多く、その子の言いたいことを探る質問をすることによってその子の本当の欲求がわかるかもしれません。
お菓子が食べたいのではなく、ただただ構ってもらいたいだけなのかもしれません。
この様な相手の隠れた欲求「ヒドゥンニーズ」を掴める人は社会的にも成功しやすいといいます。
お客さんの声には出さない本当の欲求(ヒドゥンニーズ)を察知して提案をできて喜んでもらえるのだからうまくいきますよね。
「みんなやってるよ」が自分で判断できない子を育てる



みんなやってるよ
おそらくほとんど日本人が子どものころから言われたであろうこの言葉こそが、自分で判断できない子を育ててしまうことになります。
「みんがやっている」という判断基準で生きていくとなると、進路においても、就職先やどんな仕事をするかにおいても、結婚相手においても「みんなはどうやっているのか?」という考え方がベースとなり全く主体的に生きていけなくなってしまうのはないでしょうか?
私は日々の子育てでついつい怒ってしまってひどく後悔もしてしまうこともありますが、
この「みんなやってるよ」という言葉だけは絶対に言わない様にしています。
子どもたちには「みんながどうやっているか?」ではなく「自分はどうしたいのか?」という判断基準をもって生きていって欲しいと私は思います。
「みんなやっているよ」と言いそうになったら「今は〇〇する時間だよ」と言う様に心がけましょう。
まとめ
親が子どもにどのような言葉を使うかによって将来が左右される。
と言っても過言ではないということが本書を通じて強く学ぶことができました。
普段の何気ない一言が子どもの可能性を潰してしまいかねません。
反転、何げない一言が子どもの可能性を大きく広げるきっかけにもなりるのです。
本書を通じて学べる「よくない声かけ」は実際に自分が子どもの頃に親に言われたことあるなと思うものが多いです。
自分の親を否定する訳ではありませんが、自分が親に言われたことそのまま自分の子どもに言っている限りでは歴史は繰り返されます。
日々の自分の使う言葉、子どもに対する言葉についてもっと真剣に捉えよう。そう強く思える1冊でした
是非一度手に取って読んでみてください!








コメント