ビリギャルでお馴染みの坪田信貴さんによる才能の正体について紹介します!
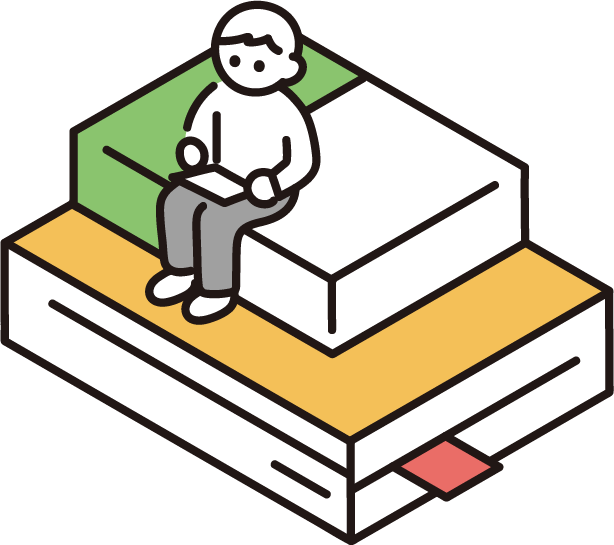
本書の概要
ビリギャルでお馴染みの坪田塾の塾長、坪田先生の考える「才能」について書かれた本です。
子育てにおける考え方や、社会人としてのマインドの持ち方やリーダーシップについても参考になる一冊となっていますので多くの方に参考になる内容です!
才能の正体 まとめ
才能は誰にでもある
よく聞く内容かもしれませんが才能というのは誰にでもあると冒頭に坪田先生は述べています。

そんなのよく聞くよ〜
と思う方もいるかもしれませんが、おそらく我々は「才能=生まれつきの能力」という固定観念に囚われて何かを成した人に対して「あの人は才能があるから、、」「地アタマがいいから、、」などと言ってしまいがちではないでしょうか?
才能というのは結果でしかない
みんな「才能=生まれもった能力」「あまり努力しなくてもできちゃう=才能がある」と考えがちですが、基本的にはみんな、何かを成し遂げたという「結果」だけを見て「あの人は才能がある」と判断しているのではないでしょうか?
実際私もインテリアコーディネーターの資格をとったのですが、それを見てありがたいことに「センスあるもんね」と言われることがありましたが、資格とったという「結果」を見て言って頂けたのかなあと感じました。
自分でいうのもなんですが資格取得のために1年以上隙間時間にコツコツ勉強を続けました。
インテリアコーディネーターの試験は図面への着色や製図の際に若干の絵心的なものが必要なのですが私は全くと言っていいほど絵心がありません。



才能があると言われる人はみんな努力している
やる気ではなく動機づけ
お腹が空いた時はご飯を食べたいという動機づけ。
勉強したくない時は、勉強せずに遊びたいという動機づけ。などなど
何かを頑張っている時だけ動機づけがあるのではなく、人はどんな時も動機づけで動いていると坪田先生は言います。
動機のない人間なんておらず、やる気はスイッチは幻想。
その人にあった動機づけがあって、正しいやり方を選んで、努力を重ねて結果を出したことにみんなは「才能がある」という。
またまた私の話で恐縮ですが「社内で一目置かれるかもしれない、、!」という動機づけがあって1年間インテリアコーディネーターの勉強を続けました。(もちろん仕事で役立つ知識がつくかもしれないというのもありますが)
結果社内から数名から「すごいね」と言ってもらい私は十分満足しました。



軽く賞賛されただけでもいい気分だよ
動機づけは認知、情動、欲求
結果を出すため必要な努力を続ける「やる気」ではなく「動機づけ」は認知、情動、欲求の行動から成り立つと坪田先生は述べています。
これならできるかも、役にたつかも、が認知
私の場合インテリアコーディネーターの問題集の1ページ目の問題を見て「できそう!」と認知できました。そこから全然知らない内容やなかなか覚えらない内容もたくさん出てきて苦労することも知らずに。
そもそも私はインテリアコーディネーターなんて絶対に取るの無理、ぐらいに思っていました。
これが「いけるかも?」という認知に変わり、世界の見え方が変わったのです。
子育てや部下のマネジメントにおいてもこのスタート時点で「どう認知をしているか?」を観察することが重要です。
テンション上がる、が情動
イヤイヤ続けていたり、おもしろくなかったりすると結局やめてしまうと思います。
「できるかも?」と思っていてやっていても続けているうちに、面白くなかったりするとテンションが上がらずやめてしまうでしょう。
私の話ばかりで恐縮ですが、インテリアコーディネーターの勉強を進めていく中で知らなかった内容を知る、わからなかった問題がわかるようになる。という単純なことであり、この小さなテンション上がる経験が情動となりました。
本当にやりたいと思うかどうか、が欲求
衝動買いなどの一時的な欲求は長続きがしないため「どうして買っちゃったんだろう」と思うことはないでしょうか?
安定的な欲求があって、「動機づけ」になると坪田先生は述べています。
またまた私の場合は「一目置かれたい」や「名刺にインテリアコーディネーターと肩書きを書きたい」などやや不純かもしれない安定的な欲求が動機づけとなりました。
「やればできる」ではなくて「やれば伸びる」
才能は誰にでもあって「正しい努力」次第で手に入るものだと坪田先生は述べております。
しかし坪田先生は「やればできる」とは絶対に言わないそうです。
たしかにやれば絶対に結果出るなんてことありません。それどころか「やればできる」という考え方だと「できない」と認知した瞬間に諦めてしまう。
やらない理由を探すのは簡単
ここまでは才能は誰にでもあり、正しい努力次第で誰でも手に入れられるものと解説がありました。
ここからは努力を続けるためのマインド的なところや、テクニック的な話となります。
7割の人は文句を言いながら死んでいく
人が死ぬ時というと周りへの感謝の気持ちいいながら死んでいくものとかを想像するかと思います。
しかしながら坪田先生のお知り合いの看護師さんの話ですが7割方の人間が死ぬ時に文句を言いながら死んでいくそうです。文句ばっかり言っている人は結局死ぬ間際まで変わらないのです。
ただ文句を一切言わない人はいません。
人間は後悔をする生き物だから、文句を言うのだと坪田先生は言います。
それを打破するためには後悔しない選択肢を選び、「やる」をやり「やらなかった」という後悔をなくしていかなければなりません。



「やらない後悔」より「やった後悔」
使い古された言葉ですが私が好きな言葉です。
もう〇〇歳だから、そんな経験ないから、とやらない理由を探すのは簡単です。
ただそうやってやらない後悔を続けて、文句を言い続ける人生になってしまう人がどれほどに多いことか。
まわりを見渡していい歳して文句ばかり言っているおじさんはいないでしょうか?
あなたなりたいおじさん像はその文句垂れ流しおじさんでしょうか?
尖った部分を磨けば選択肢は広がる
これからの時代は仕事を選ぶのではなく創る時代です。
尖った部分を丁寧に磨けば選べる仕事や職業の選択肢が増える。
自分が尖っていないところは別の誰かが補ってくれるためバランスよく尖る必要はありません。
あなたの持っている能力はある人からは意味がないものかもしれませんがある人からは絶賛される可能性を秘めています。
他責にした時、才能の芽は消える
うまくいかない理由を「誰かのせい」にするのはやめましょう。
他責にしてしまったときに才能の芽はたちまち枯れてしまうと坪田先生は言います。
誰かのせいにしてしまっている時点で実は自分で自分を否定してしまっており、誰かのせいにするではなくしっかりと自分を見つめることが重要です。
自分自身やまわりを見渡してみてもついいろいろなことを「誰かのせい」にしてしまっていることは多い様に思います。
誰かのせいにすることは楽だからなのかもしれません。会社のせい、上司のせい、先生のせい等々。
なんでも周りや環境のせいにするのではなく、他人事ではなく自分ごとで捉える視点が重要です。
できる人の言葉は聞く意味がない
名選手が名監督にならないことが多いのと同様に、できる人は自分がどうしてそれができているのかがよくわかっていないことが多い。
そのためできない人に対して説明ができないどころか、なんでできないのか?とイライラが募ってしまう。
行動を完コピする
営業なら営業のやり方を教えてもらうのではなく一緒に営業先へ同行して、できる人がどのように普段営業をしているのか観察して行動を完コピすることが成績上昇に直結します。



完全には真似ができない
真似をするなんて恥ずかしい、、なんて思う人もいるかもしれません。
しかしどんなに真似をしようとしても自分らしさはでてしまうもの。
そこで勝手に自分らしいオリジナリティが生まれ、個性となります。
一番影響力のあるのは家族
どれだけ優秀な子どもでも努力が継続できないと伸びません。
その継続を支えるのも、邪魔をするのも家族なのです。
子どもが夢をもって努力を始めようとした時、「そんなの無理だ」などと否定せずに信念を持って見守る。愛情を与える、温かく見守る。
子どもの才能を開花させるにはこれつきます。
またこれは上司と部下にも通づる部分があり、上司は黙って部下の成長を見守ることが部下の成長につながります。
100点より0点の方がいい
考えてみれば当たりませですが100点のテスト(たまたま自分が知っていたことばかりが出たテスト)と0点のテスト(たまたま自分が知らなかったことばかりが出たテスト)では0点のテストの方が自分を成長させてくれます。
0点のテストで知らなかったところを、できなかったことを学んでいく。
これをやることことで確実に伸びます。
しかし実際0点をとってしまうと復習しようとも思わなくなってしまうもの、、
How型、Why型
この時に大事なのがHow型で考えることです。
「全然わからなかったテストをどう次に活かしていくか?」
これを習慣化できることよってぐんぐん能力を伸ばして、尖らしていくことが可能です。
一方why型が
「全然わからなかったから」「そもそも無理だから」
といできなかった言い訳ばかりが出てしまいその「やれない理由」が「やらない理由」になってしまいます。



やらない理由を探すのは簡単
中立的で客観的なフィードバック
人はフィードバックをうけるとよくなろうとする生き物。
しかし多くの人はこのフィードバックの方法を間違えてしまっております。
フィードバックは客観的な事実のみ
背筋の曲がってい子どもへは「背筋まがっているね」
肘をついて食事をしている子どもへは「肘ついてるね」
このようにプラスの意図もなくマイナスの意図もないただ事実のみを言う。
「背筋伸ばせ!」「肘つくな!」のように命令をする必要はないのです。
部下の才能を伸ばすのも中立的なフィードバック
同じことが上司と部下の関係でも言えます。
自分の価値観を入れずにひたすら中立的なフィードバックを心がける。
自分の価値観を入れずにフィードバックを行うことで、部下が持っている「自分が正しいと思っている価値観」の通りの姿になっていきます。
否定をしたり自分の価値観を押し付けてしますと合わないと感じた人は離れていってしまいます。
自分で気づくことが成長への一番の近道
客観的なフィードバックをつづていると自分で気づく力が養われます。
これが「メタ認知」でありこの能力がつくと能力がぐんぐんと伸びていき「才能」となります。
自分がどのように認知しているかを認知することが「メタ認知」です。
今自分の認知はどのような状況なのかを認知して客観視する。それにより自分自身でフィードバックできる様になります。
そもそも人は自分が正しいと思っており、人に対して指導というものはできないため、とにかくフィードバックを行い自分で気づいてもらうしかないのです。
教育、指導、改善を受けると悪感情が芽生える
教育、指導、改善は教える側と、教えられる側がいて成り立っています。
ただ教育、指導、改善またはフィードバックをしてきた相手に対して、相手との信頼関係がないと受けた方は攻撃されていると感じてしまいます。



信頼関係の大切さについて書籍の中で詳しく解説されているから読んでみてね
指導する側と指導される側はいつもずれている
指導する側は正しいと思っていても、指導される側はやり方や存在を否定されたかのように感じる。
このことから主観をもったフィードバックや、指導は絶対ダメ!
指導する側は指導してやっている!という感覚は捨てて、客観的で中立的なフィードバックを心がけましょう。
まとめ



中立的で客観的なフィードバック
この内容が本書を読んだ上で印象的であり、即実行に移せる内容だなと強く感じました。
どうしても自分の子どもに対して、「〇〇するな!」「〇〇しなさい!」と言ってしまいがち。
この本を読んでからそんな言いたくなる気持ちをぐっとこらえて、極力皮肉っぽくならない様に「〇〇だね」と子どもの状況をそのまま伝えることを意識しています。
すると思いの外、「〇〇するな!」と命令をしてしまった時より効果がある様に感じています。
これこそ自分がどのように認知しているか認知する能力「メタ認知」が養われているのでは、、、!
と思わず期待してしまいます。
子どもも大人もやらされているばかりでは成長できません。
自分で気づいて行動していってこそ成長できるのだなと強く感じます。
本書の中には坪田先生が坪田塾で一緒に働く仲間を面接して採用する話や、坪田先生と吉本興業の大崎会長とのエピソードなどなど参考になる内容がたくさんあるかと思いますので是非一度手に取って読んでみてください!








コメント