千葉ロッテマリーンズ・吉井理人監督による『機嫌のいいチームをつくる』をご紹介します。
プロ野球の現場で実際に成果を上げた監督が語る“チームづくりの極意”とは?
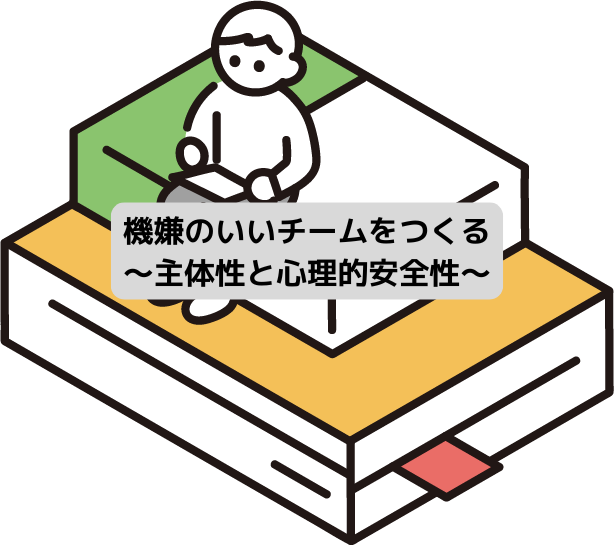

5分ほどで読める記事になっています
著者について
2023年にロッテの監督に就任後、前年5位のチームを2位へ躍進。
2024年も3位と2年連続Aクラス入り。
選手時代は1997年にメジャーへ挑戦し通算32勝。
2003年に日本球界に復帰後、2007年で現役引退。(日米通算121勝、62セーブ)
2008年から日本ハム、ソフトバンク、ロッテで投手コーチ。
今ほどメジャーに挑戦する選手が少なかった時代にメジャーへ挑戦し実績を残されているピッチャーです。
また私が子どものころ初めてサインをもらったプロ野球選手であり、気さくに対応してくれたのを今でも鮮明に覚えています。



こんな人におすすめです
- 千葉ロッテファンの人
- 人をマネジメントする立場にある方(マネージャー・リーダー職)
- •野球ファンで、将来的にマネジメントを目指している方
機嫌のいいチームをつくる まとめ
自主性ではなく主体性をもたせる
自主性と主体性の違いはわかりますでしょうか?
自主性・・当然なすべきことを自分から進んでやろうとする様子
主体性・・自分自身の意思や判断に基づいて行動する様子
主体性には自分の意思や判断が含まれているが、自主性には含まれていない。
野球界にも指導者に言われたことを積極的にできる選手は多いが、アドバイスを受けずに自分の強みや弱みを自分で考えることのできる主体性のある選手は少ないと吉井監督は言います。
私も含め会社員の場合も会社から言われたこと、上司から指示をされたことを積極的に、忠実に業務を遂行できる人間は多いと思います。
しかし吉井監督の言う、自分の意思や判断に基づいて主体性をもって仕事に取り組めていますでしょうか?
主体性をもって、自分で決定をして取り組んでいると、人に決められたことをやるよりモチベーションが異なります。
うまくいかなくても、自分で決めている場合振り返りにより何が悪いのか認識がしやすく、モチベーションが持続する期間も変わる。
適度な緊張感
私が学生だった頃の部活動や、入社したての頃は、先輩後輩によるパワーバランスによる恐怖心の植え付けや、抑圧がもはや「ふつう」なレベルでした。
学生のころから個人的にこの「先輩後輩のパワーバランスによる抑圧」に違和感を覚えておりましたが、コンプライアンスが叫ばれる昨今ではいい意味で薄れてきた組織も多いのではないでしょうか?
しかしこのような「パワーバランスによる抑圧」やパワハラがなくなったことで、協調性が持てず、自由を履き違える若者が多くなっている。
主体的になろうとするとエゴイスティックになってしまい、自分の良いと思ったことを自由気ままにすると解釈をしてしまいがちなのが日本人の悪い癖。
このような時代の今に必要なのが「パワーバランスによる抑圧」ではなく「適度な緊張感」
パワハラはあってならないが、それを避けるあまり協調性や結束力への意識が薄らぎ、協調性を持てずにて自由を履き違える若者が多くなっている。
とはいえ今の時代は厳しい指導や、パワハラはあってはならないことであり、恐怖心ではなく緊張感。
これは管理職などの人より、我々の様な下の層の人間が意識をする必要があるのではと感じました。
自由を履き違えず、適度な緊張感を持って上司に接する。
私はとくに優しすぎてみんなからいい意味で「舐められている」様な先輩や上司に対しては丁寧に接するように心がけています。
コンプライアンス全盛の時代に管理職の層ではなく、我々の様な現場の層も意識しなければなりません。
「代行」のスキル
選手の感覚に迫るには観察をするだけでなく、「代行」のスキルが必要。
本書でいうところの「代行」とは「相手の立場に立って物事を考える」
選手に対してコーチングを行う際には自分の経験を語ることなく、できるだけ選手の口から出るように仕向けていく。
上司、先輩からの過去の成功体験談って退屈ですよね。



このおっさん何言ってんの?
と思われたら信頼関係は築けません。
選手の考えを受け入れ、選手の感覚を理解することが重要。



そう考えているのか、なるほどね
たとえ自分の考えて異なっていても頭ごなし否定をしない。
自分が間違っていたら素直に誤りを認める。
私の経験談ですが、若手時代に上司へわからないことを聞いた際に、その上司も分からないことがありました。
その際、その上司は素直にわからないことを認め、「一緒に調べよう」という姿勢を取ってくれたことに非常に信頼感を抱いた経験があります。
とはいえいまだに無意識のプライドからなのか素直に自分の無知を認められず、その場しのぎのごまかしアドバイスをする様な上司も多く存在します。
無知や間違いを素直に認められる上司の方がステキではないでしょうか?
心理的安全性を高める
チーム力を高めるにはよく言われる「チームのキズナ」は必要ありません。
心理的安全性が担保されたチームを築くことが重要です。
打ち合わせや会議の際に「間違ったことを言ったらどうしよう、、」という感覚から発言できなかった経験はないでしょうか?
これは「間違ったことを言っても大丈夫」という心理的安全性が担保をされていないからです。
会議では色々な立場の人間の、色々な意見を出し合うことが重要です
会議の主催者である上司やマネージャーは「間違いはない」という前提を提示し、心理的安全性を担保させた状態で進行することがとても重要です。
若手社員の一見突拍子のない意見の中に大きなヒントがある可能性だって十分ありえます。
逆に経験豊富なその道のプロの意見ばかりでは、間違ったアイデアはなくとも、新鮮なアイデアは出にくいでしょう。
まとめ
心理的安全性を担保し、選手が主体的に考え、自ら気づき、行動する。
プロ野球の監督による書籍ですのでプロ野球チームをベースに語られていますが、一般の社会、ビジネスにも十分置き換えられる内容でした。
自主性と主体性の違い。
学校教育や部活動の経験から「言われたことはきっちりやる」という自主性の高い人は多いかと思います。
実際自分の会社の人間を見渡しても自主性に長けている人は多くいます。
上司やマネージャー、後輩を指導する立場の人であるならば、いかに主体性を持って行動をする人間の多い組織にしていくか?
基本的には監督目線の話なので「どう導いていくか?」という部分にフォーカスをしています。
しかしまだ管理職の立場でない私の様な人間にとっては、「主体的に動くことの重要性」も学ぶことのできる一冊でした。
「心理的安全性」と「主体性」があれば、チームはもっと強くなる。
野球も、職場も、同じです。
是非一度手に取って読んでみてください!









コメント