今日はひろゆきさんの「1%の努力」について紹介します!
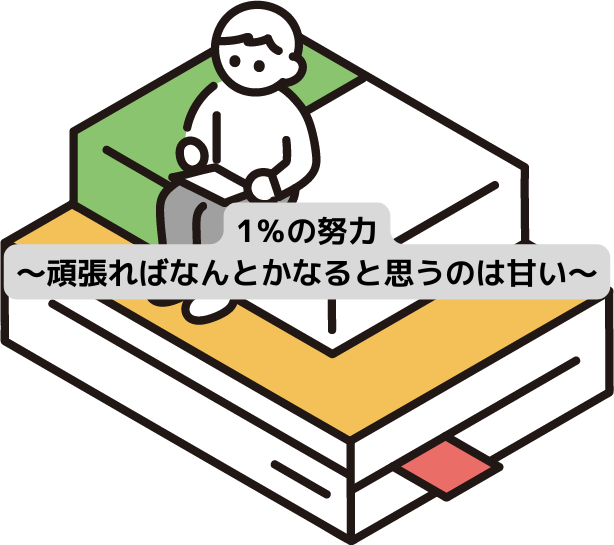

5分ほどで読める記事となっています
考え方の考え方
働かないアリの様に自分には「サボる才能」はあるか?
それを磨いていくためのひろゆきさんなりの考え方が学べる一冊となっています。
目的は「幸せの総量」を増やすため。
いわゆる一般的な会社員が歩む様なレールを外れてきたひろゆきさんなりの生き方、考え方。
「頑張ればなんとなかなる」と思っている人は甘い。



こんな人におすすめです
- 頑張っているのに報われないと感じる人
- 効率よく成果を出したい人
- 無駄なことをやりたくない人
1%の努力 まとめ
ヒマは全力で作る
常にスケジュールがパンパンで忙しそうな人、パンパンにしておかないと気がすまない人。
この様な人、あなたのまわりにいないでしょうか?
しかし「チャンス」というものは突然やってきます。
こんな時にスケジュールがパンパンで余裕がない場合、「チャンス」を逃してしまうことになるでしょう。
「チャンス」は一瞬で目の前を通りすぎます。



時間は余るものではなく、作るもの
私は普段、営業の仕事をしていますが常にスケジュールには余白を作る様にしています。
余白を作ることで顧客からの急な依頼事にも即時に対応をすることができ、結果的に大きな成果に結びついたりとチャンスを掴めることが多いと感じています。
しかし余白を作りすぎると上司や同僚に「あいつ仕事してる?」と思われかねないので、適度に忙しいフリをすることは欠かせません。
第三者的なところを探る



現場の人間と企画側の人間
会社でもよくあることかもしれませんがいくら現場側の人間が文句を言って企画側や経営側を説得しても、現場側が厄介者として扱われてしまうことが多いでしょう。
そこで上流から下流まで知っている第三者的なポジションが有利となります。
下っば仕事で愚痴ばかり言っているなら、経営側として自分だったらどうするか考える。
店長の様な仕事だったら、現場の仕事で知らない部分がないか考える。
その様な第三者的なところを探ることによって、頭ひとつ飛び抜けることができる。
第三者的なポジションを取るために必要なのは
- 現場のリアル
- 経営者側の論理
- コミュニケーションコスト
会社に入れば、まず現場の仕事をやることが多く、そこから優秀な人はマネージャーなどの経営側の論理に傾いていく。
3つ目の「コミュニケーションコスト」とは「言ってはいけないことを言うスキル」
例えば「〇〇ってうまくいきますかね?」と相談された時に「うまくいかないな」と思った場合にちゃんと「失敗するよ」とそれを伝えてあげられるかどうか?
もちろん感情的にいうのではなく、根拠を示したり、改善策を一緒に考えたりすることは大事です。
もしその場合でうまく行った場合は「ごめんなさい」と謝ればいい話。
謝れば修復可能です。
それでも嫌みを言ってくる人とは仲良くなる必要はないでしょう。



本音で言って、ちゃんと謝る
みんな同じことしか言わない
アメリカ人は自己主張し、日本人は空気を読む。
日本では人と人の距離が近いため、あえて職場から離れて一人の時間を作ったり、他の人と接触をしない生活を送る。
そのように意図的に一人に時間を作らないと自分の意見を作れない。
私の会社はフリーアドレスなのですが、以前私がよく座っていた席の近くによく座っている人が、いわゆる「みんなと同じこと」を大きな声でよく言っている人でした。
それが耳に入ってくるのが嫌で、比較的静かな人が多い席に座ることを心がけると集中力も増すのはもちろんですが、色々な逆張り的なアイデアも浮かんできて打ち合わせでも積極的に発言できるようになったりと好循環が生まれました。
「みんなと同じことばかり言っている人」の近くにいると逆張り的な考えができにくくなります。
ちょっと違う視点からモノが言えるようになれば頭ひとつ抜け出せるでしょう。
世の中全て「ネタ」である
仕事がうまくいかなくても、恋愛がうまくいかなくても、お金がなくても、、笑いながら話せばネタになる。
その時は本当に大変だったことも今は笑い話、なんてことは誰にもあるかと思います。
そんな笑い話を何個作れるか?
という考え方を持てるようになれば、何かチャレンジしようかどうか判断に迷ったときなどに
「失敗してもネタになる」ぐらいの気持ちを持つ事ができれば一歩踏み出すこともできるようになるのではないでしょうか?
その先に失敗ではなく、明るい未来が待っているかもしれませんし。
まとめ
タイトルに「1%の努力」とあるようにいかにサボりながら生きていくか?というひろゆきさんなりの考え方の考え方を深く学べる一冊でした。
「サボる」というといかにもほとんど努力をしないように捉えてしまう人もいるかもしれませんが私は本書を通じてそのようには感じませんでした。
例えば著書の中では「あらゆることを調べつくせ」と書いてあります。
調べる労力を惜しんでいるとNISA、ふるさと納税などの得する制度を活用できなかったり結果的に損をしてしまいます。
いかに「サボる」かではなく、いかに「正しい方向性で無駄なく努力をするか」ということが大事だな学べました。
是非一度手に取って読んでみてください!









コメント