今日は幸せになる勇気を紹介します!


5分ほどで読める記事になっております。
愛し、自立し、人生を選べ
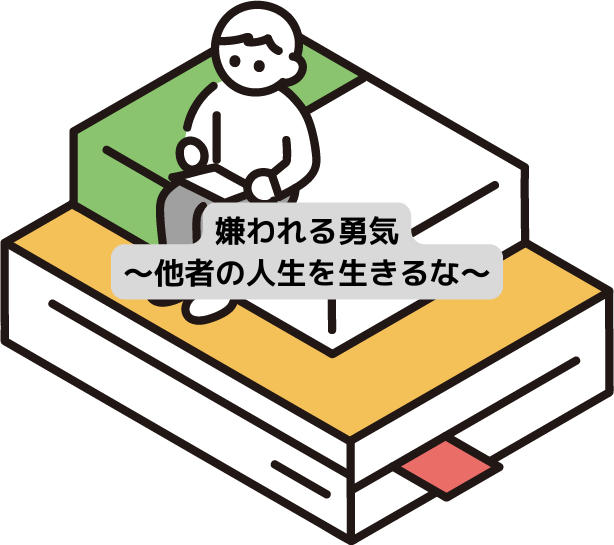
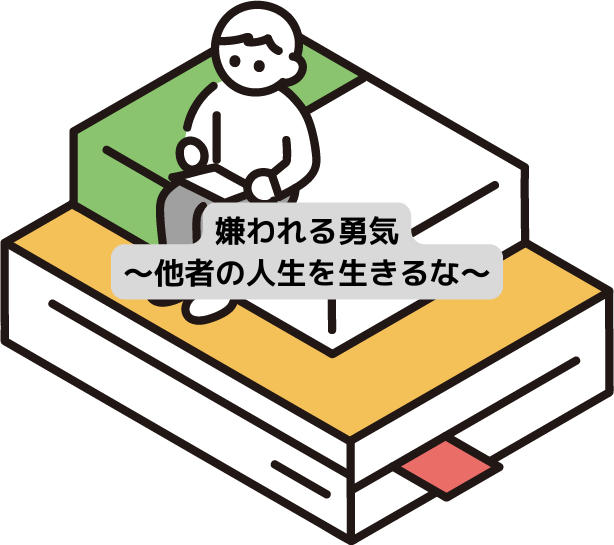
言わずとしれたベストセラー「嫌われる勇気」の続編です。
嫌われる勇気の3年後、再び青年は哲人の書斎を訪れます。
図書館司書から学校の先生となった青年は「アドラーの思想はとんだペテンだ」と言って乗り込んでくるところから始まります。
「幸せになる勇気」ではより実践的な、教育や愛にフォーカスした内容をとなっております。



こんな人におすすめです
- 嫌われる勇気を読んだ人
- 親、教師、会社の先輩となる立場など教育に携わる立場の人
- 人間関係に悩んでいる人
幸せになる勇気 まとめ
教育の入り口は「尊敬」
部下が上司を、生徒が先生を、いわゆる「教えられる側」が「教える側」を尊敬することではなく
「教える側」いわゆる先生、上司が生徒や部下を尊敬すること。
教育が目標とすることは自立であり、その入り口として尊敬の念をもつことが必要です。
尊敬なきところに良好な人間関係は生まれません。
また尊敬とは「ありのままのその人」を認める。これに勝る尊敬はありません。
怒りにまかせて言うことを聞かせる行為は、服従をさせているだけで怒りの嵐が去るのを待っているだけです。
他者の関心事に関心を寄せる
尊敬をするための具体的なアクションとして「他者の関心事に関心を寄せる」ことをあげています。
大人から見たら何がおもしろいのか?というような事に関心をもっているのが子どもというものです。
そんな子どもの行為に眉をひそめるのではなく、どんなものか理解しようとする。
なんなら自分も一緒にやって遊んでみる。
このときに大事なのは「遊んであげる」のではなく自分自身も「楽しむ」
このとき初めて子どもは子ども扱いされているのではなく、「尊敬」をされていることを実感するでしょう。
これは子どもだけでなく、あらゆる人間関係においての尊敬の具体的な第一歩。
アドラー心理学で重要な考え方である「共同体感覚」を理解する上でも、他者への関心というのは重要なテーマとなります。
叱っても、褒めてもいけない
子どもが何か問題行動を起こす時、叱る場合もあるかと思います。
しかしアドラー心理学では賞罰を否定します。
子どもが問題行動を起こす理由とは、
「それがよくないことだと知らない」という可能性が高いです。
実にシンプルですが知らないのであれば教える。
その際に叱責の言葉はいらないのです。
子どもを叱っても叱っても問題行動がなくならない、なんてことはよくあることはないでしょうか?
また自分が子どもや学生の頃に何度も叱られても懲りずに問題行動を繰り返していた経験はないでしょうか?
このことが「叱る」ということが有効ではないことの証です。
自立という目標を掲げる
特に我々の様な世代は親や教師から「あーしろ、こーしろ」と言われることが多かったかも知れません。
このようにいわゆる他者からの指示のもとに行動をする経験が多い結果、
「他者の指示」を仰いで生きる方が楽になってしまいます。
これでは自立どころではありません。
自分では何も決められない子どもにしない為に教育者は常に自立という目標を掲げなければなりません。
「遊びに行っていいか?」「おやつを食べてもいいか?」の様なことを親が禁止するのでは、自分で決めていいんだと教えること。
自分の人生、行いは全て自分で決定する。
冒頭にも出てきた「尊敬」の念があれば、「自分で決められるのか?」という疑いの念も持たず自分で決めさせることができるでしょう。
自らの価値を、自らが決定をすることが「自立」であり、「私であること」に価値を置ける、そんな人間になれる様に教育ができればよいでしょう。
与えよ、さらば与えられん
他人のことが信じられないのは自分を信じていないから。
自分を愛することができなければ、他者を愛することができません。
他者を信じられなければ所属感も得られず、交友の関係にも踏み出せません。
しかし「課題の分離」でもあったように、他者が自分のことをどう思うかについては一切のコントロールができません。
まずは目の前の人に信頼を寄せて、仲間になる。
分かり合えぬ存在として他者を信じるしかないのです。
「人と会話するのが苦手だから」「異性と会話するのが苦手だから」と言って待っているだけでは友達も恋人もできません。
待っているだけではなく、自分から行動し関心と尊敬を寄せなければなりません。
「与えよ、さらば与えられん」
引用:幸せになる勇気
愛とは築きあげるもの
映画やドラマ、はたまた飲み会の席で語られる様な愛や恋愛について話。
このような話は運命的な、「恋におちる」様な表現をされることが多いかと思います。
これは本質的には物欲と同じです。
アドラーは他者から愛される技術ではなく、能動的な他者を愛する技術を解き続けました。
あなたの周りに出会いがないと嘆く人はいないでしょうか?
この1年の間に誰とも出会わなかった人はいないでしょう、その出会いを何らかの「関係」に発展をさせるのは勇気が必要です。
その勇気を出す事もせず、もっと理想的な運命の人がいる、、という幻想に逃げる。
運命の人はいないのです。
運命の人に出会いさえすれば、うまくいくはずだ、、という可能性の中に生きてはいけません。



出会った時に結婚するだろうなと思いました
この類のことを言う人っていると思いますが本当なのでしょうか?
この様なことを若いうちから耳にすることで、運命の人という幻想に取り憑かれてしまうのかもしれません
愛することは決断であり、運命は自ら作り上げるものです。
まとめ
教育や人間関係において「尊敬」、「自立」、「愛」を軸にして学びを与えてくれます。
「教える側が相手を尊敬する」というところは子育てにおいても、会社などの組織においても取り入れる価値のある考え方ではないでしょうか。
他者を変えようとしたり、愛してもらおうとしたり我々はつい求めてしまうものです。
しかし本書では自ら愛することや、信じる勇気、与える勇気の大切さを教えてくれます。
他者の関心事に寄り添い、自分から信頼を示し、愛することを決断する。その積み重ねが、よりよい人間関係や本当の幸せにつながるのかもしれません。
幸せになることに、特別な才能や条件は必要ない。ただ、自らの選択と行動によって、人生をより良くできる。そんなシンプルで力強いメッセージを受け取れる一冊でした。
ぜひ一度手に取って読んでみてください!









コメント